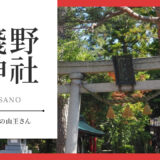【概要・由来】
国造神社は、天平勝平3年(751年)に創建されたと伝えられています。
当時の国造(こくぞう)という地方の長官が、自らの氏神として大兄彦命(おおえのひこのみこと)と大國主命(おおくにぬしのみこと)を祀ったのが始まりとされています。大兄彦命は、日本神話に登場する天孫族の祖であり、大國主命は、日本列島の国土や豊穣を司る神です。
平安時代には、菅原道真大人(すがわらのみちざねたいじん)が加わりました。
菅原道真大人は、学問や文芸の守護神として知られる天神様ですが、当社には、彼が左遷された際に国造の地に立ち寄り、当社に参拝したという伝説があります。その際に、彼が書いたという「国造神社参詣記」や「国造神社詩」などの文献が残っています。
江戸時代には、加賀藩主前田家の庇護を受けて栄えました。特に初代藩主前田利家公は、当社を虚空蔵之宮とも称し、自ら所蔵していた虚空蔵菩薩像を奉納しました。また、歴代大聖寺藩主の松平家も当社を崇敬し、多くの寄進を行いました。
明治時代には、近隣の春日神社と合祀されましたが、昭和時代に分離されて現在の場所に遷座しました。現在は、金沢市泉2丁目21-6に鎮座しています。
【虚空蔵菩薩像について】
虚空蔵菩薩像は、現在は国造神社の境内にはありません。かつては、初代藩主前田利家公が所蔵していたものを奉納したため、当社を虚空蔵之宮とも称していましたが、明治時代に井手神社と合祀された際に、虚空蔵菩薩像は井手神社に移されました。現在は、井手神社の本殿に安置されています。井手神社は、金沢市泉3丁目にあります。
虚空蔵菩薩像は、絹本着色の仏画で、平安時代の12世紀に描かれたとされています。虚空蔵菩薩は、虚空のように広大無辺の福徳と智慧をもち、それを人びとに与え、願いをかなえるという密教の神です。像は、頭に宝冠をかぶり、胸に法衣をまとい、左手に錫杖(しゃくじょう)、右手に宝珠を持っています。背後には光背があり、周囲には八大童子が描かれています。この像は、東京国立博物館に所蔵されていますが、井手神社の本殿には複製品が安置されています。
東京国立博物館で虚空蔵菩薩像を見ることができますが、常設展示ではありません。特別展や企画展などの際に、時々展示されます。
詳細な情報は、東京国立博物館のウェブサイトをご覧ください。
【摂社 菅原神社について】
菅原神社は、国造神社の摂社で、金沢市卯辰山町に鎮座する神社です。菅原道真大人を祀っています。この神社は、文政3年(1820年)に、妓楼が公許された際に、卯辰茶屋町で営業が行われたことに由来します。当時、観音町西源寺の後に菅原道真大人を祀り、芸妓たちの鎮守の神としました。後に現在地に移転しました。境内には、太い梁の社殿や歴史を感じさせる狛犬が一対向かい合っています。
【鎮座地】
金沢市泉2丁目21-6
【電話】
076-241-0713(春日神社)
【拝観料金】
無料
【祭神】
大兄彦命(おおえのひこのみこと)
大國主命(おおくにぬしのみこと)
菅原道真大人(すがわらのみちざねたいじん)
【行事】
1月1日 元旦祭
1月3日 どうじゃん祭
1月7日 七草祭
2月3日 節分祭
2月11日 建国記念日奉祝祭
2月25日 大國主命例祭
3月17日 菅原道真大人例祭
4月29日 昭和天皇御誕生奉祝祭
5月3日 憲法記念日奉祝祭
5月5日 こどもの日奉祝祭
6月30日 大兄彦命例祭
7月30日 夏越大祓式
8月15日 終戦記念日奉祝祭
9月23日 秋分の日奉祝祭
10月17日 例大祭
11月3日 文化の日奉祝祭
11月23日 勤労感謝の日奉祝祭
12月31日 大晦日除夜の鐘
【見どころ】
境内には、菅原道真大人が参拝したという石碑や、加賀藩主前田家から寄進された狛犬や灯籠などがあります。また、春には桜やツツジが咲き、秋には紅葉が美しいです。
【神徳(御利益)】
国造という地方の長官の氏神であることから、国家安泰や地域繁栄などの御利益があるとされています。また、菅原道真大人は学問や文芸の守護神であることから、学業成就や芸能上達などの御利益も期待できます。
【駐車場・アクセス】
駐車場は神社の少しだけ離れた場所にあります。
アクセスは、JR金沢駅からバスで約20分、野町停留所下車、徒歩約5分です。
【授与品・御朱印】
御朱印やお守り、絵馬などの授与品を頒布。
御朱印は、春日神社の本殿で受けることができます。
お守りには、国造神社の御神紋である「三つ鱗」が描かれています。
絵馬には、菅原道真大人の姿や筆などが描かれています。
【ウェブサイト】
 金沢 寺社仏閣めぐり
金沢 寺社仏閣めぐり