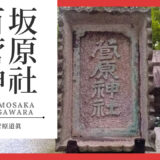歴史・概要
大乗寺の歴史 – 永平寺、總持寺と深い繋がりを持つ禅の道場
大乗寺は、古くは椙樹林(しょうじゅりん)、後に金獅峯(きんしほう)とも呼ばれた、由緒ある曹洞宗の寺院です。
その開山(創始者)は、永平寺の第三祖である徹通義介禅師(てっつうぎかいぜんじ、1219~1309)です。
徹通義介禅師と永平寺中興
徹通義介禅師は、師である道元禅師(1200~1253)の教えを受け継ぎ、「貧」の学道を重んじました。
その後、中国に渡り各地を巡り、「永平十刹図(えいへいじっさつづ)」(旧国宝・重要文化財指定)を著しました。
帰国後、永平寺の寺の規則や伽藍(寺院の建物群)を一新し、「永平中興(えいへいちゅうこう)」と呼ばれる功績を立てました。
これは、永平寺の再興とも言える大きな出来事です。
平成20年には、徹通義介禅師の700回忌にあたる御遠忌が盛大に執り行われました。
大乗寺の開創と瑩山紹瑾禅師
大乗寺は、永平寺の門葉(門下)の四つの代表的な寺院の一つにも数えられています。
徹通義介禅師は後に加賀の地に移り、守護職であった富樫氏の帰依を受け、正応2年(1289年)に野々市に大乗寺を開きました。
さらに、徹通義介禅師のお弟子である瑩山紹瑾禅師(けいざんじょうきんぜんじ、1268~1325)は、大乗寺の第二祖となり、その後、羽咋市の永光寺、そして大本山總持寺を開きました。
瑩山禅師は、日本で最も多くの寺院を有する曹洞宗の基盤を築いた人物として、道元禅師を高祖(こうそ)と仰ぐのに対し、太祖(たいそ)と仰がれています。
つまり、道元禅師が曹洞宗の教えの根本を築いたのに対し、瑩山禅師はその教えを広く普及させたと言えるでしょう。
このように、大乗寺は永平寺、總持寺の両大本山と非常に深い繋がりを持つ寺院なのです。
江戸時代の移転と「規矩大乗」
江戸時代に入り、今からおよそ300年以上前に、加賀藩の重臣であった本多家の庇護のもと、現在地に移転しました。
この時期には、26世中興の月舟宗胡禅師(げっしゅうそうこぜんじ)と27世復古の卍山道白禅師(まんざんどうはくぜんじ)が現れ、道元禅師の古風を尊重し、清規(僧侶の修行規則)を整え、「規矩大乗(きくだいじょう)」の名を世に知らしめました。
「規矩」とは、物事の基準や手本という意味で、「規矩大乗」とは、大乗仏教の修行の規範という意味合いを持ちます。
これにより、大乗寺は禅の厳しい修行道場として、その名を高めていきました。
現在も大乗寺専門僧堂が運営されており、修行僧が日々修行に励んでいます。
現在の伽藍と参禅
大乗寺の伽藍は、日本の禅宗建築、特に曹洞宗寺院建築の典型的な七堂伽藍の配置を示しており、仏殿は国の重要文化財に指定されています。
その他、多くの建物が県や市の指定有形文化財となっています。
現在、大乗寺には多くの人々が心の支えを求めて参禅に訪れ、また、境内の静かで落ち着いた雰囲気に触れ、自分自身を見つめ直そうとする人々が年々増えています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
大乗寺の仏殿は、山門の奥に建ち、法堂・庫裏・僧堂と回廊で繋がっており、棟札によって、元禄15年の上棟であることが知られています。
低い基壇の上に建ち、入母屋造り、平入り、本瓦葺き。
床は漆喰叩きの土間とし、角柱を用いるなどかなり簡略化していますが、禅宗様を主とした建物で古式をしのばせるものがあり、禅宗寺院の伽藍の中心建物としての雰囲気をよく伝えています。
住所
〒921-8114
石川県金沢市長坂町ル-10
電話
076-241-2680
拝観料金
本堂など伽藍内可能
有料(500円(伽藍内に上がる場合。要予約))
拝観時間
9:00~16:30(4月~11月)
9:00~16:00(12月~3月)
宗派/山号・寺号
曹洞宗/東香山(とうこうざん)/大乘寺
本尊・寺宝
本尊:釈迦如来坐像(重要文化財)
寺宝:「大乘寺文書」(国の重要文化財)
御朱印
御朱印は、拝観時にいただけます。
行事
大乗寺では、年中行事が行われています。
1月
新年祈祷・大般若転読(修正会)
正月の三日間、毎朝、大般若経という全600巻のお経を転読(折本を転翻させる)して、今年一年の世界の平和、国土の安全、参詣者の心願成就を祈念。法要の後、仏前にそなえられた祈願の般若札が配られる。
寒行托鉢
寒の入りから節分までの寒中の1ヶ月間、修行僧が一日の休みもなく一軒一軒戸口で読経して歩く行。二十余名の修行僧が禅宗古来の衣にわらじに網代傘で歩く姿は、それだけで金沢の冬の風物誌として親しまれ定着している。
2月
涅槃会だんごまき (2月14日)
2月15日の涅槃は梵語のニルバーナ、煩悩を吹き消すの意味でお釈迦様ご入滅の日。お釈迦様追慕の法要の後、本堂一杯の参詣者に涅槃だんごが撒かれ、無病息災のお守りとして重宝されている。
3月・9月
彼岸会
彼岸は梵語パーラミタ(波羅蜜多)の音写語で彼岸に到るの意味。彼岸の中日の前後6日間で、布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智智慧の六波羅蜜を実践して、迷いの世に救いの世界を実現しようと願う一週間。
4月
花まつり(降誕会)・動物諸霊供養 (4月8日)
花まつりは、おしゃかさまのお生まれになった日として、仏教徒は、お祝いを行う。
世界に新しい光がかがやくこの日、大乘寺では、犠牲となった多くの生きものたちに対して、まごころをもって合掌し、法要をおつとめし、感謝と懺悔のおもいをこめて、ご供養する。
7月
孟蘭盆法会
お盆は先祖のみ霊が帰って来る日と言われている。八月盆の地方も多いが金沢は七月。大乘寺の隣には野田山という公営墓地があって室生犀星や鈴木大拙などの著名人も。一説では35万基ともいわれる墓があり、お盆の墓参りは想像を越えた賑わい。
10月
開山忌 10月14日
大乘寺は1289年ご本山永平寺三代目住職であった徹通義介禅師によって開かれた。この徹通義介禅師のご命日を偲んで報恩の供養を勤める。このとき永平寺開山道元禅師、ニ祖孤雲懐弉禅師そして徹通禅師とご三方のご霊骨が仏前に安置される。参詣者に昼食が用意される。
12月
成道会摂心(臓八摂心)
お釈迦様は六年間の修行の末、菩提樹の下で覚悟の坐禅に入り12月8日未明にお悟りを開かれ仏陀となられた。この跡かたを慕って12月1日から8日朝まで、摂心という集中坐禅を行じ自覚を新たにする。一般の方の参加も歓迎している。
除夜の鐘
一年間つい知らぬ間に犯してきた身と口と心との罪、その108といわれる煩悩を108声の鐘の音で一つ一つ清めていく。この清められた身心で新しい年の出発を願う。一人一声ずつついて戴く。
見どころ
大乗寺の見どころとしては、国の重要文化財に指定されている仏殿や、県・市の指定有形文化財に指定されている建物があります。
隣接している野田山墓地には前田利家の墓があります。
大乗寺保存樹林
境内には紅葉が美しいとされる場所もあります。
春には大乗寺丘陵公園の桜が綺麗に咲き、多くの方々が花見に訪れます。
1月の小寒から始まる寒行托鉢は金沢の風物詩になっています。また2月14日の涅槃会には大勢の方がお越しになり涅槃団子の功徳をお持ち帰りになられます。大乘寺は静かな山の中にあり、自分を見つめ直したいと多くの方が参禅に訪れ、こころのささえになっています。
(曹洞宗公式サイトより)
伽藍(がらん)
「伽藍」とは、簡単に言うと、お寺の主要な建物群のことを指します。
もともとはサンスクリット語の「サンガラーマ(僧伽藍摩)」という言葉が語源で、「僧侶が集まって修行する静かで清らかな場所」という意味を持っています。それが中国に伝わり、「伽藍」と略されるようになりました。
伽藍は単に建物を指すだけでなく、僧侶が修行生活を送るために必要な施設全体を意味します。
- 総門: 黒門、寛文5年(1665年)建立、石川県/金沢市指定有形文化財
- 山門: 江戸時代初期、石川県/金沢市指定有形文化財
- 仏殿: 元禄15年(1702年)、重要文化財(国指定)
- 法堂: 元禄10年(1697年)頃、石川県/金沢市指定有形文化財
- 碧厳蔵(へきがんぞう): 金沢市指定有形文化財(「碧巌録」を収蔵するための蔵)
- 本多家霊廟(れいびょう): 金沢市指定有形文化財(天皇や皇族または由緒ある家系の祖先などの霊を祀るための建物、つまりお墓)
重要文化財
- 仏殿
- 支那禅刹図式(寺伝五山十刹図)
- 仏果碧巌破関撃節(一夜碧巌集) :『碧巌録』
- 三代嗣法書
- 韶州曹渓山六祖壇経(紙背仮名消息):通称、大乗寺本
- 羅漢供養講式稿本断簡 道元筆
・山門の裏には「しあわせの鐘」と名付けられた鐘があり、誰でもつくことができます。
・門には威圧感ある仁王像があります。大きなわらじもあり、そのオーラで身が引き締まる思いになります。
駐車場・アクセス
寺院の駐車場、大乗寺丘陵公園の駐車場があります。
IRいしかわ鉄道線金沢駅から車で20分
最寄り駅は北陸鉄道バス「長坂町」バス停
金沢駅から北鉄バス26番泉野出町一丁目行き、長坂台下車徒歩約9分
または、香林坊から北鉄バス26番または81番泉野出町一丁目行き
ウェブサイト
大乗寺のウェブサイトは以下です。
http://www.daijoji.or.jp/
曹洞宗のサイトページ
https://www.sotozen-net.jp/temple/32
この投稿をInstagramで見る
 金沢 寺社仏閣めぐり
金沢 寺社仏閣めぐり