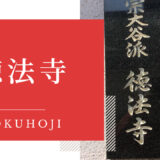【概要・由来】
この神社は、非常に古い歴史を持つ「延喜式内社(えんぎしきないしゃ)」です。
「延喜式内社」とは、平安時代中期に編纂された法律書「延喜式」の中の「神名帳」というリストに記載されている神社のことで、当時、朝廷から重要な神社として認められていたことを意味します。
つまり、この神社は1000年以上も前から存在し、国からも認められた由緒正しい神社なのです。
創建は神護景雲2年(768年)と伝えられています。これは奈良時代にあたります。
当初は、村の東に位置する額山(ひたいやま)に鎮座していました。
この神社は、中世にこの地域を支配した守護大名である富樫家から手厚い崇敬を受けました。
富樫家は、神社の建物の造営を行ったり、神社に寄進(お金や物などを奉納すること)をしたりするなど、神社を大切にしました。そのため、この神社は額(ひたい)七ヶ村の総社、つまり、この地域一帯の中心となる神社として広く知られるようになりました。
その後、富樫氏の内乱(後富樫氏の兵乱)によって社殿が焼失してしまったため、現在の場所に移されました。
明治時代に入り、明治41年(1908年)9月18日には、道勲社(みちいさおしゃ)という別の神社が合祀(ごうし)されました。
また、明治33年(1900年)には郷社に列格されました。
郷社とは、近代社格制度において、村や町などの地域における中心的な神社として位置づけられた社格です。
延喜式内神社。神護景雲2年の創立、往古は村の東に当たる額山に鎮座。守護富樫家の崇敬も厚く、社頭造営ならびに社料の寄進もあり、額七ヶ村の総社と伝えられる。後富樫氏の兵乱に際し社殿焼失したので現地に遷座したといわれる。明治41年9月18日道勲社を合祀。明治33年郷社に列格。
【鎮座地】
金沢市額谷町ロ130-1
【電話】
076-248-0826(林郷八幡神社)
【拝観料金】
不明
【祭神】
伊邪那岐命、国底立命
【行事】
春祭:3月17日
秋祭:10月17,18日
新嘗祭:11月23日
【見どころ】
社殿は江戸時代後期の建築で、本殿は入母屋造り、拝殿は切妻造りである。
境内には道勲社や稲荷社などの末社がある。
【神徳(御利益)】
不明
【駐車場・アクセス】
駐車場は不明。
北陸鉄道石川線乙丸駅から徒歩約12分。
【授与品・御朱印】
林郷八幡神社にお問合せ
【ウェブサイト】
石川県神社庁
https://www.ishikawa-jinjacho.or.jp/shrine/j0798/
この投稿をInstagramで見る
 金沢 寺社仏閣めぐり
金沢 寺社仏閣めぐり